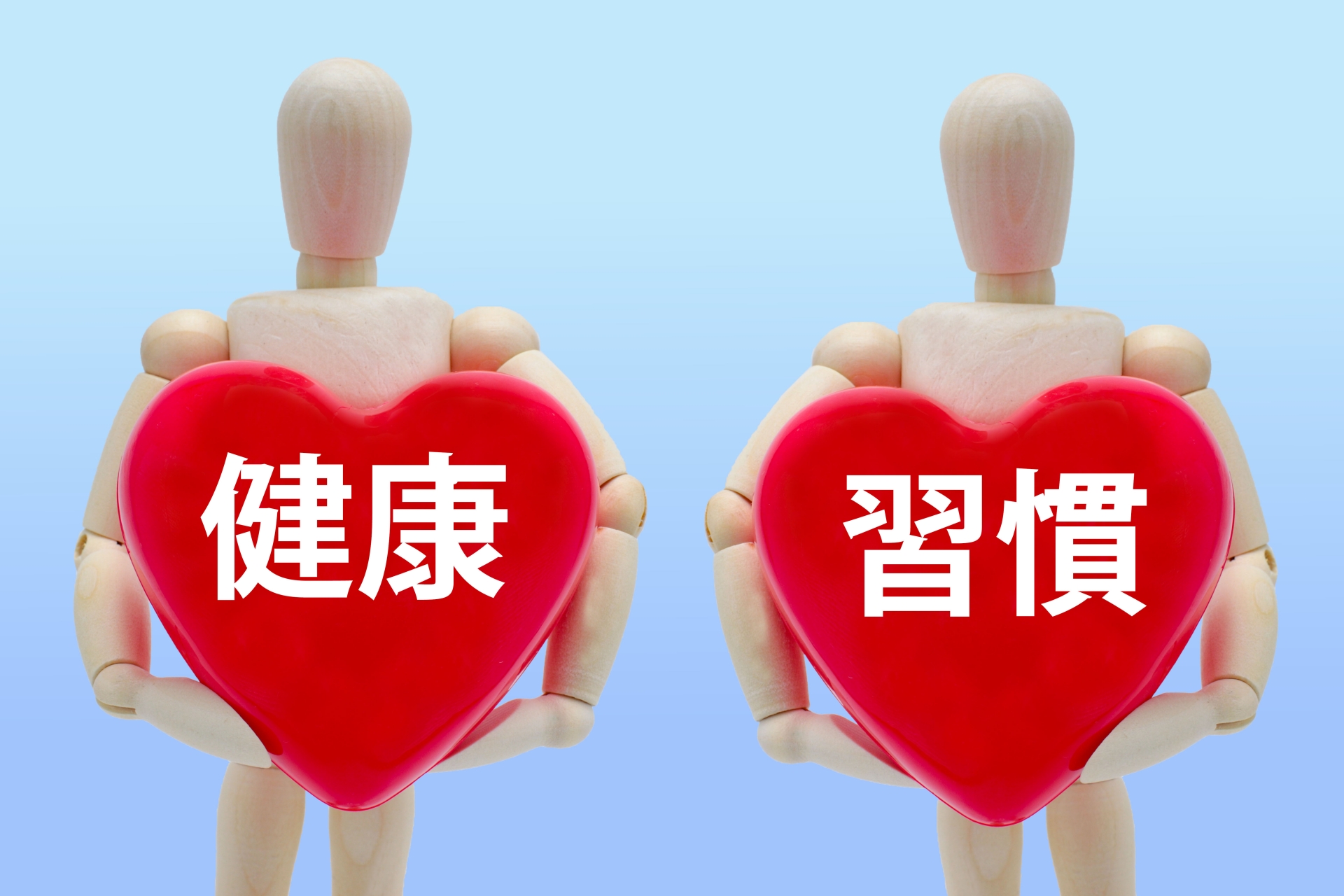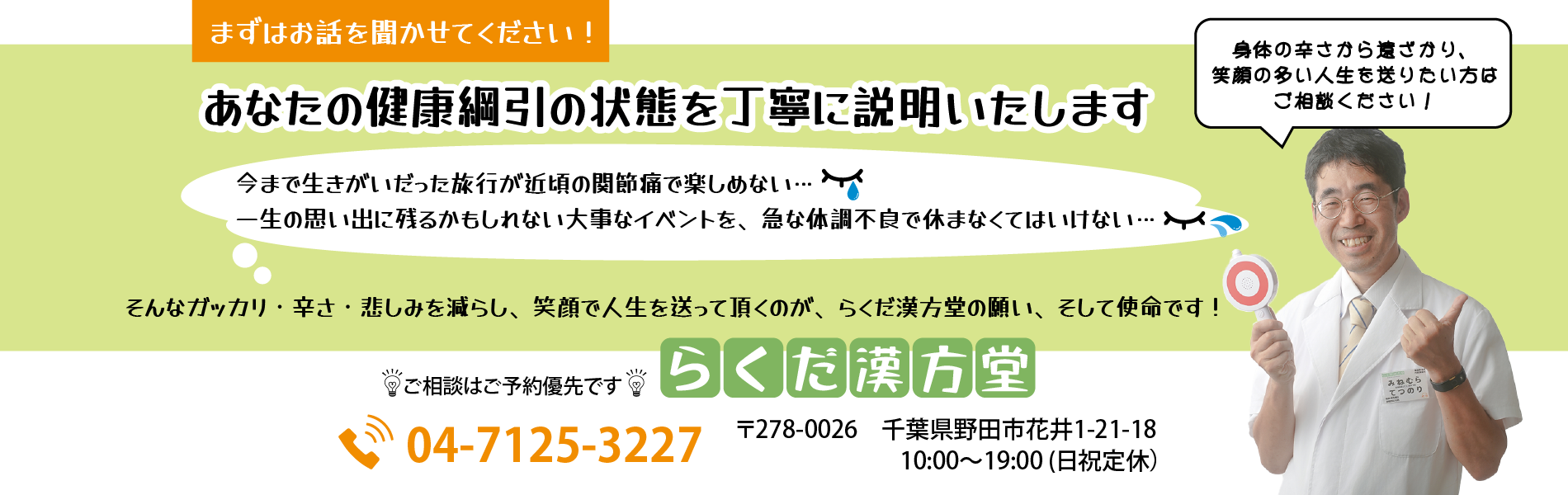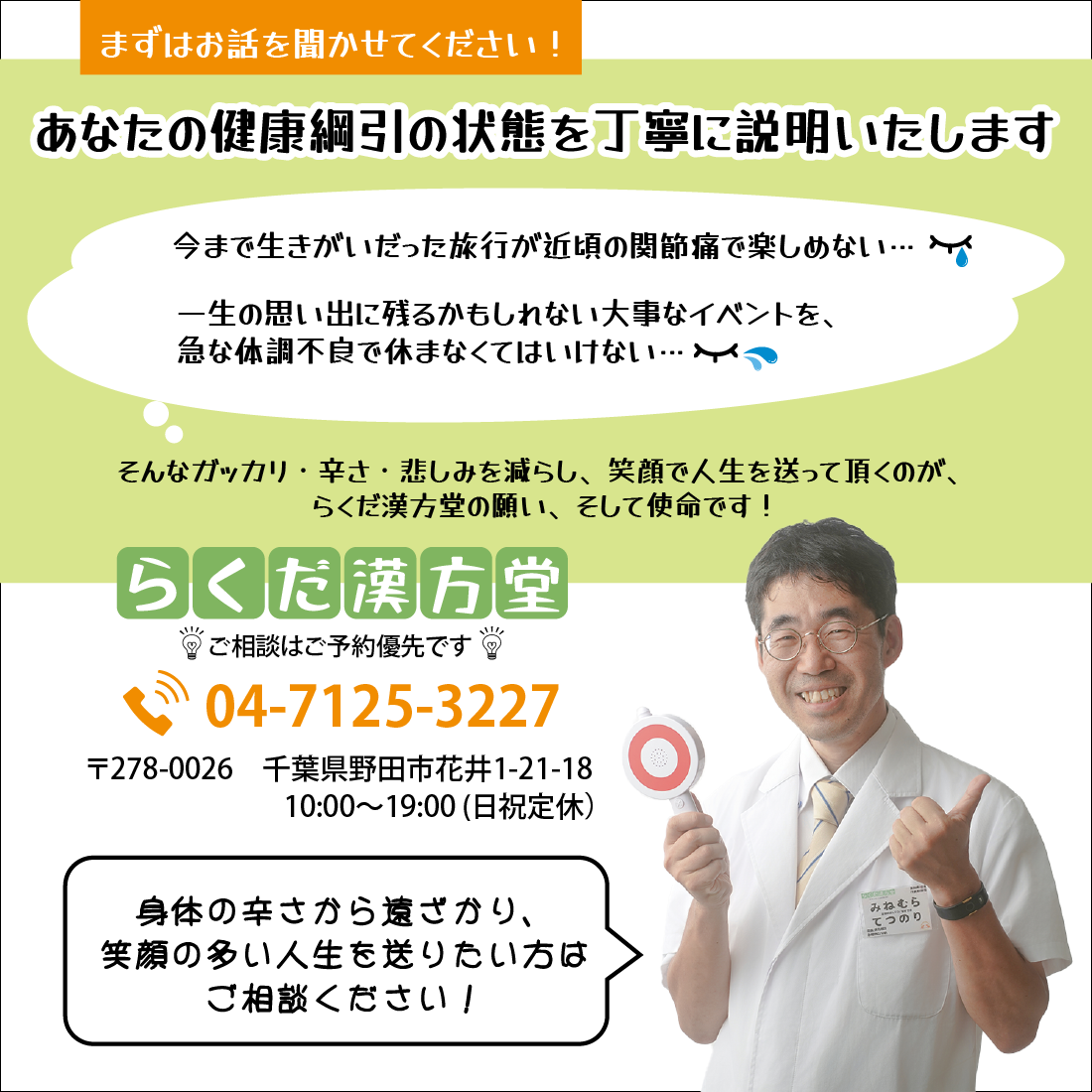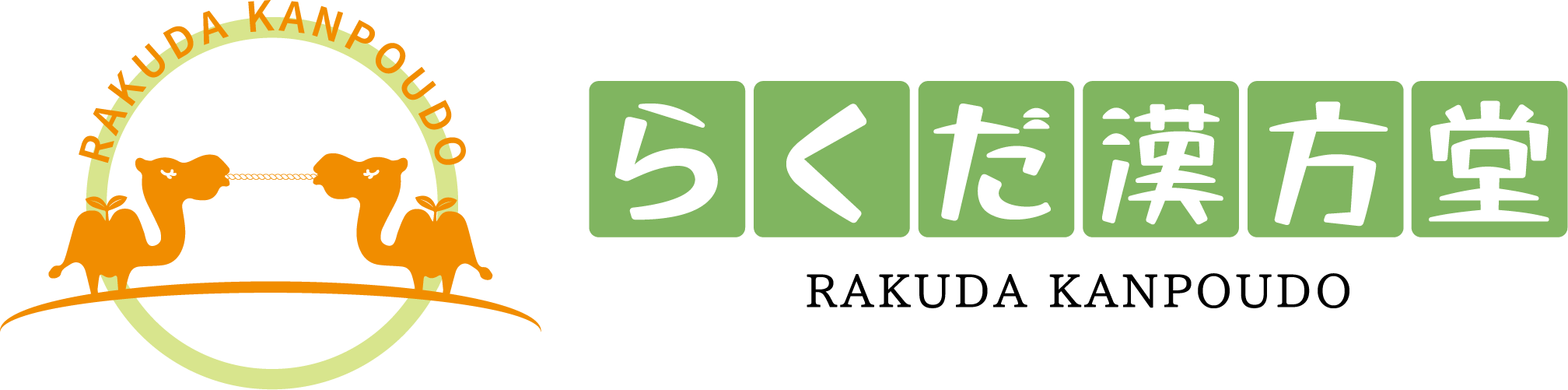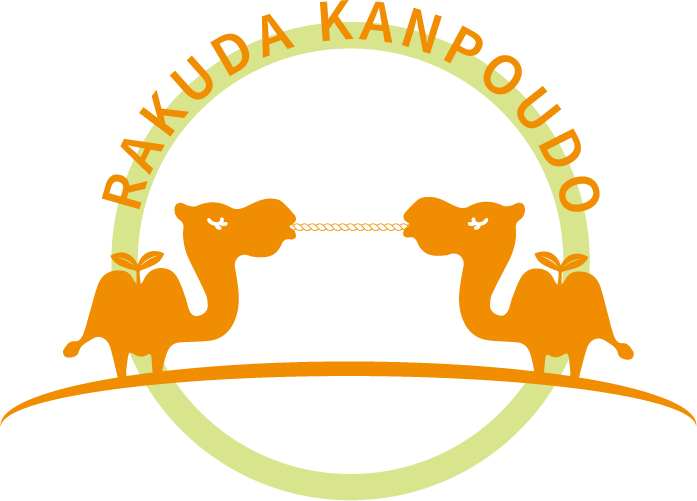
「ぐっすり眠りたい!!」不眠症・入眠障害
~らくだで変わる、あなたの睡眠・そして人生~
- なかなか寝付けない…
- 夜中に目が覚めてしまう…
- 一度目が覚めるとその後眠れない…
- 眠剤や安定剤で寝付けてるが、依存症や副作用が心配…
など、不眠の原因は人それぞれ。当店にも不眠症でお悩みの方は沢山いらっしゃいました。
らくだでは、あなたの不眠のタイプに合わせて、適切な処方を行います。
分子栄養学に基づいた睡眠に必要な栄養補充と、漢方薬で不眠の原因になっている体質の歪みの改善を目指し、心身のリラックスを促し自然な眠りを誘います。
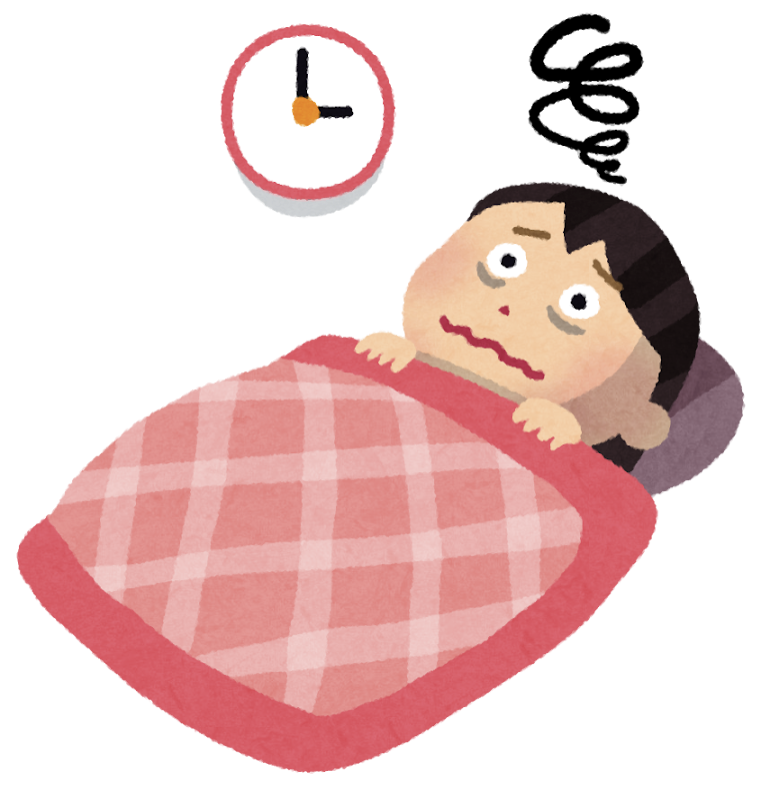
不眠症・睡眠障害の原因あれこれ
一口に不眠と言っても、その原因は多数存在します。不眠の原因が沢山あるというのは悩ましい反面、現在不眠で悩んでいる方にとっては改善への道筋が沢山ある、ということでもあります。
ここでは不眠の原因について、西洋医学と東洋医学の両面から大まかに見ていきましょう。
◼️睡眠物質が作れない・働かない
不眠の原因として、私達に睡眠を促す「睡眠物質」が量的・質的に機能不足である、というものが考えられます。
睡眠物質の量的な機能不足とは、文字通り睡眠物質の量が足りていない、という事です。睡眠物質には「メラトニン」「セロトニン」「GABA」「PGD2」「アデノシン」などが挙げられますが、これらの物質が眠りに導く為に必要な量が足りてない、という事ですね。
睡眠物質の質的な機能不足とは、量としては足りている睡眠物質が、何らかの理由で十全に機能していない、という事。睡眠物質という宝の持ち腐れ状態ですね。一般の方がこの様な視点を持つのはなかなかに難しく見落としがち。ですが、それゆえに睡眠改善の突破口にもなり得る手段でもあります。
◼️興奮物質が過剰に働く
私達は寝たい時に寝たい一方で、活動したいときには活動していたいですよね。その「活動したい時に活動を促してくれる」脳内物質=興奮物ですが、寝たい時には睡眠の妨げにもなります。
脳内における「寝るための働きかけ」より「活動するための働きかけ=興奮物質の作用」が過剰に働く、それが不眠の原因になっている可能性も見逃せません。
◼️中医学で考える不眠症・入眠障害の原因
西洋医学の分子レベルのメカニズムとは異なる視点で不眠の原因を探ることも、不眠の改善には有効であり、この時漢方=中医学の知恵が役立ちます。具体的には、不眠=脳の機能障害、という以外の観点から不眠の原因を探ることですね。
具体的には、不眠の原因を「身体の機能を司る五臓=肝・心・脾・肺・腎」の働きが不眠とどう関わっているのか、そこから原因を探っていきます。

不眠症・睡眠障害を誘発する日常生活
不眠の原因は日常生活にも多数潜んでおります。その一例を挙げてみましょう。
- 就寝直前までスマートフォンやパソコンを使用する
- 夜遅くに食事や間食をとる
- 不規則な睡眠習慣を続ける
- 就寝前にカフェインやアルコールを摂取する
- 寝室の環境を整えない
この辺りは「わかってはいるけど…」という内容がほとんどではないでしょうか。ですが「わかっているだけ」の知識は何の役にも立たないばかりか「わかっちゃいるけどやめられない」という事実がストレスにもなると考えたら害悪ですらあります。
不眠症・睡眠障害の対策あれこれ
不眠の原因をいくつか挙げてきましたが、これら不眠の原因はそのまま改善の道しるべにもなります。その道しるべを探っていきましょう。
◼️睡眠物質を作る・働かせる
睡眠物質の不足はそのまま不眠の原因に直結するため、不眠の改善には欠かせないポイントの一つですが、睡眠物質の主力「メラトニン」は日本では一般での入手は困難「GABA」は脳内に直接行かないため摂取しても無駄などの問題があります。
一方で睡眠物質の大半は「脳内で作られるもの」。であれば睡眠物質の量的・質的改善は「材料の積極的な摂取」と「材料をもとに睡眠物質を作る」環境を整える事が大切。これが整えば睡眠物質が働きにくい状況も付随して整ってきます。
◼️興奮物質の働きを防ぐ
不眠の原因は睡眠物質だけでなく興奮物質にもあります。グルタミン酸は直接的に、活性酸素は様々な働きを介して間接的に不眠の原因になります。
これらの働きをある程度防ぐ事も不眠の改善に繋がります。
◼️中医学で考える不眠症・入眠障害の対策
不眠の原因を身体機能の不調、具体的には「五臓の働きの失調」と見ると、様々な解決法が見えてきます。情緒を司る「肝」「心」の働きを見直したり、睡眠を妨げる物質「痰」を生み出す「牌」の働きを改善する…
不眠の改善を目指して焦る気持ちも無理はありませんが「急がば回れ」という格言もあります。この機会に体全体の調子を見直してみてはいかがでしょうか?

不眠症・睡眠障害の改善に繋がる日常生活
不眠の原因が日常生活に潜んでいるのと同じく、改善の糸口も日常生活から見えてきます。いずれも医学的・生物学的に根拠がある内容です。
- 朝日を浴びる
- 規則正しい食事をとる
- 適度な運動を行う
- 入浴のタイミングを調整する
- 就寝前にリラックスする時間を設ける
私達の健康状態を作るのは、何と言っても「生活習慣」。今の健康状態は私達が今までどれだけ自分自身の身体を大事にしていたか、その成績表であり、「体に良い事悪い事」の綱引き勝負の結果です。
なるべく「睡眠に役立つ事」を増やし「睡眠を妨げる事」を減らす事。それらを張った分良い結果が早く訪れますよ。
不眠症・入眠障害体験談
~ぐっすり眠れる・眠りで困らない生活に戻った喜びの声の数々~
※末尾は旧「野田ジャーナル」掲載時の号数
当店でお世話させて頂いた、不眠で悩んでいた皆様の体験談を一部ご紹介致します。

◼️夜中に3回トイレ起床・耳鳴り目眩も併発した不眠症
~不眠症:60代・女性(NJ0862号)~
3年位前から夜中に3回位トイレに起きる。その頃から耳鳴りやめまい・また不眠がちになった。加齢で身体のつくりが弱くなってきている。とくに腎の働きが弱くなっているため膀胱・耳に症状が現われて…
腎精というエネルギーを補給すると症状も改善するので、補腎剤を中心に服用していただく。
約10日位で症状の改善がはじまる。
◼️心配事で不眠症に…胃腸と腎の働きが衰えホルモン分泌も低下…
~不眠:60代・女性(NJ1099号)~
心配事で肝の働きがバランスを失って不眠に、胃腸が弱く貧血気味で不眠、腎の働きが落ちて眠れるホルモン分泌が低下し不眠になったり、五臓と不眠は深く関係しています。
この方は若い頃から胃腸が弱く不眠がち、5~6年前からレンドルミンを服用しているが「自然の眠りを得たい」とご相談にいらっしゃいました。
漢方薬とミネラルを服用し約40日、レンドルミンなしで「自然に眠れて朝の目覚めが気持いい」との事。
◼️睡眠薬で眠ってる日々から卒業!朝もスッキリさわやかに!
~自然に眠りたい:70代・男性(NJ1269号)~
長い間、睡眠薬を飲んで寝る生活が続いてる。できれば薬を飲まないで自然に眠れれば一番いいが。
とご相談にいらっしゃいました。
8月下旬からお医者さんの薬と、心と腎の働きを良くして不眠を治す漢方薬を一緒に飲んで頂きました。
11月上旬には「自然と眠れるようになりました。朝もスッキリさわやかです」とご報告頂きました。よかったですね♪
◼️不眠・胃痛・食欲不振・頭痛…いろいろあった症状から元気に
~不眠・胃痛・食欲不振・頭痛:20代・男性(NJ1465号)~
一年前の2月頃から体調不良で6月頃から通院し胃薬を飲んでいた。最近、さらに悪化し眠れず朝ひどく疲れている。胃痛もあり食欲も無い。
頭痛もあって倒れてしまうのではと心配になり、近所の方の紹介でご来店。
不眠や胃の痛みにもよい漢方薬とミネラルをお飲み頂いたところ、4日後には「すっきり、元気に起床して食事も摂れた」と大変お喜びでした!
◼️20年以上熟眠できず、寝てもすぐ目が覚めてたのが改善!
~ぐっすり眠りたい:80代・女性(NJ1530号)~
長いこと(20年以上)ぐっすり眠りたいと思っているが、眠るとすぐ目がさめてその後眠れない。何か良い漢方薬があれば飲んでみたいとご相談に。
らくだでは腎の働きを補う漢方薬などを服用頂く。
約1か月後「この漢方薬は私に合ってるみたいで良く眠れる」と漢方薬をお求めに。
睡眠でお悩みの方は、西洋の眠り薬を飲む前に早めにご相談ください。